子連れで駐在生活に奮闘中の皆さん、お子さんの日本語の勉強頑張っていますか??
人間、成長とともに年齢に見合った語彙を増やしていかないと、思考力がつかなかったり社会で理解できることが増えていかないものです。
本だとどうしても子供の好みばかりでジャンルが偏ってしまうので最近は子ども新聞を読ませています。
子ども新聞のメリットは何といっても様々なジャンルの語彙が身につくこと、時事に強くなることだと思っています。
子ども新聞とは?
子ども、特に小学生向けに大手新聞社が発行している新聞のことです。
イラストや図解を使ってわかりやすく時事ニュースを伝えたり、コラムや様々な学習コーナーがあり親子で楽しめる新聞です。
ある調査によると、子供新聞を読んでいる子は読んでいない子よりも成績が良いとのデータも出ており今注目を集めています。
低学年の子供でも読めるようにルビがふってあるのが普通で、子供が興味を持つように各社様々な工夫をして作られています。
海外で読める子ども新聞3社
オンラインで配信するものは国内サービス限定というものが多いですが、今回紹介するのは海外在住の方限定で読める子ども新聞です。
登録してみたけど国外からは見れなかった…ということがないので安心ですね。
読売KODOMO新聞
2020年6月12日、つい最近の話ですが国内で発行部数No.1の読売KODOMO新聞が海外への配信を開始しました。
読売KODOMO新聞の魅力は毎週木曜日に週一回のみ発行のため子供が無理なく読めるところ。
文字を読むことにまだ慣れていない新聞初心者におすすめです。
全ページオールカラー、ページ数は20ページなので一日に少しずつ読んでいけそうなボリュームですね。
小学館と協力して編集しているので図鑑のような見やすいレイアウトも子供を引きつける理由の一つです。
未就学児~中学生まで多くの読者に支持されています。
大手進学塾「四谷大塚」とコラボしており、中学受験対策にもなるそうですよ。
中高生向けには読売中高生新聞というものも発行されています。
内容はさらに充実して思考力や判断力、表現力を鍛える教材としても活用できると評判です。
電子版料金
- 読売KODOMO新聞:一部$1.99、一か月$6.00
- 読売中高生新聞:一部$2.99、一か月$8.00
- 読売KODOMO新聞+読売中高生新聞セット:一か月$12.00
国内から申し込みできません
ふりがながないものがあるけど?
読売KODOMO新聞では漢字を読めるようになる、ある工夫がされています。
一度出てきた感じにはルビをふらない、一年生で習う漢字にはルビをふらないなどです。
こうすることで紙面が真っ黒になることを防ぎ、読みやすくしており、わからない漢字は読みかえして自分で探すことで自然と漢字を読めるようになるのだそうです。
朝日小学生新聞
朝日新聞の特徴は何といってもタブレット等での閲覧だけでなく、PDF版も配信されるのでプリンターで印刷が可能だという点です。
印刷しておいてあげると子供は見やすいですし、お気に入りの記事は切り取ってスクラップブックを作ったり、後で読み返したりといろいろな活用方法が考えられますね。
一日8ページと程よいボリュームなのも嬉しいです。紙面は様々なコーナーから形成されているので、最初はマンガや興味のある部分だけでも読ませてみましょう。

毎日文字に触れる、新聞を読むという習慣をつけるのにはぴったりな子ども新聞ですね。
内容は多少難しいのかなと感じるものの、きちんとルビもふってあるので小学一年生から始めるという方が多いようです。
朝日新聞といえば天声人語というコラムが有名ですが、小学生新聞では天声こども語といってその子供版が掲載されています。
これを毎日書き写すだけでも読解力につながると評判です。
購読者のお母さんの85%以上も愛読しているというデータがあるほど、大人が読んでも楽しく、ためになる新聞です。
忙しい中高生のために、高学年向けの新聞は週刊新聞となっていますので、時間のある時にまとめて読むのも良いですね。
電子版料金
毎日小学生新聞
1936年創刊、子ども新聞の先駆けとなった新聞です。電子版は国内外問わず申し込みをすることが可能です。
これまでは上で紹介した2社とも電子版を配信していなかったので、在外日本人の子供たちは毎日小学生新聞を読むしか選択肢がありませんでした。
つまり、これまで最も多くの在外日本人に読まれてきた新聞でもあります。
年齢的には特に3年生~6年生から支持を得ていますが、漢字には全てルビがふってあるので小学校一年生から読むことは可能です。
毎週日曜日には5歳~小学二年生を対象にした漫画が掲載されていたり、土曜日には中高生向けの新聞、15歳のニュースデジタルも配信されます(小学生新聞の料金に含まれます)。
今さら聞けない…という中学生や大人が読むにもおすすめですよ。
ジャーナリストの池上彰さんなど豪華執筆陣によるコラムや、今後大学入試などで重視されるだろう「正解のない問いに答える力を育む」を意識したコーナーも必見です。
電子版料金
- 毎日小学生新聞:一か月(日刊)1610円
- 15歳のニュースデジタル:一か月(週刊)100円
申し込みはWebサイトにて
読売KODOMO新聞を実際に購読してみた。感想、メリットとデメリット
筆者は小2の息子にKODOMO新聞を購読することにしました!
こども新聞は初めてだったこともあり、いきなり毎日は読めないだろうと考え週刊にしました。
感想とメリット
カラーで見やすく、写真もふんだんに使ってあり、子供の目を引く新聞は大人が読んでも楽しいです()()
しかし、やはり文字が小さいので、読書が苦手な子にとっては自分で読むのはまだまだ難しいと感じます。
そのため我が家では朝の時間や土日に子供と一緒に読んでみたり、親が先に読んで面白かった話題をシェアするということが多いです。
海外にいてもニュースはネット上で見れますが、子供に興味のある話題を自分で選んで子供にわかりやすくかみ砕いて説明することはなかなか難しいものです。
その点、こども新聞は難しい言い回しを全て子供にもわかりやすく言い換えてあるので、
そのまま読んであげるだけでも世界や日本国内で話題になっている出来事を簡単に子供とシェアすることができます。
読んでみたテーマについてどう思うか聞いてみたり、簡単なディベートをすることで、普段から考える機会、意見を述べる機会が増えたと思います。
語彙が身に着けばいいなと思って始めたこども新聞ですが、子供と話す話題が広がったことは意外なメリットでした。

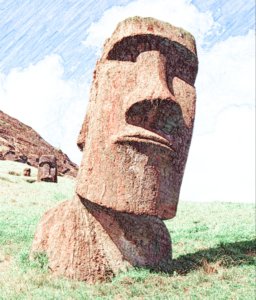
デメリット
電子版なので紙に慣れ親しんでいる(?)親世代にとっては多少読みにくいという点かなと思います。
できればパソコン、最低でもタブレットで読むことをおすすめします。
ブルーライトを浴びるので読むのは夜寝る前を避けるのが良いでしょう。
朝日小学生新聞であればPDFの印刷ができます。毎日印刷するのは多少手間ですが、
印刷すればスクラップブックを作ったりと後で見返すことも可能なので活用の幅が広がります。
筆者は子どもが小学校高学年になったら朝日小学生新聞に挑戦したいと考えています。
新聞を読むコツ
環境づくり
例えば朝起きたらまずは新聞を読む、学校から帰ってきたら読む、土日に読む、などの習慣をつけるために環境づくりから始めましょう。
ダイニングテーブルなど目につきやすいところにタブレットや印刷した新聞記事を置いておき、すぐ読めるようにしておくとGOOD!
大人が先に読んでおく
子どもに見せる前に大人がさっと目を通しておいて、面白かった記事や印象に残った記事を子供におすすめしてあげましょう。
ただ「読んでおきなさい。」と言われるよりも「これ面白かったよ。」と言われる方が興味がわくものです。
子どもが読めたらそれを話題にして親子のコミュニケーションを深めましょう。
読んだ感想を言いあうなどして意見交換をしてもよいですね。
大人と一緒に読む
子どもだけで難しそうであれば最初は読み聞かせをしましょう。
一文ずつ交代で読む方法もおすすめです。慣れてきたら徐々に自分で読む長さを増やしていくとよいですね。
低年齢であれば、見出しだけ読ませたり、漫画だけ読ませたりするだけでも良いと思います。
興味が湧けば他のコーナーも自然と読み始めます。
まずは毎日5分、それだけで年間1825分も文字を読むことになりますので何もしないのと比べると大きく差が開きそうです。
興味を持ったことにほめる
どんなことでよいのでお子さんが興味を持ったことに対して褒めてあげましょう。
褒められることでドーパミン(やる気ホルモン)が出て、また次も読んでみようという気にさせてくれるそうです。
活用例
声に出して読む
日本の小学校では音読の宿題が出ることが多いと思います。簡単な記事でも良いので音読の宿題に追加してみてください。
普段使わない文字にたくさん触れることで読解力が身に着きます。
書き写す、感想を書く
見出しだけでも良いので書き写してみましょう。
日本の小学校や中学校で作文を書く機会ってアメリカに比べて極端に少ないと思いませんか?
アメリカではライティングの授業があり、自分の意見を書く機会がとても多いと思うのですが、
日本の学校教育では作文はあまり重要視されていないと思います。
なので、中学受験をする日本の小学生などは子ども新聞を使って作文対策をしているそうですよ!
受験をするしないに関係なく、自分の意見を簡潔に文章にまとめることはアメリカでは必須スキル。
まずは書き写すことから始めて、簡単でも良いので感想も書く習慣を身につけるようにできると良いですね。
スクラップブックを作る
興味のあるジャンルだけを集めてノートにまとめたり、感想を書いたりしておけば、後から読み返せて理解も深まるのでお勧めです。
おわりに
余談になりますが、我が息子が6歳の時、現地校の社会科見学で一人全く理解ができず、ただただ聞き逃す作業をしていたという悲しい経験があります。(母はボランティアで見ていました)
大人が経済新聞を読むにしてもそうですが、予備知識がないと話の内容はなかなか理解しにくいものですよね。
ましてや言語が母国語ではないのですから、全く頭に入ってこないのも無理はありません。
なのでできるだけ様々なジャンルで母国語の予備知識をつけてあげることが海外での学校生活において成功の第一歩ではないでしょうか?
特にアメリカではSTEAM教育に力を入れているので、Science(科学)、 Technology(技術)、 Engineering(工学)、Mathematics(数学)の予備知識はあればあるほど良いですね。
母国語で予備知識があれば多少単語がわからなくても話の流れが理解できるため、外国語を理解するうえでメリットは大きいです。
帰国後スムーズに日本の学校、社会に溶け込むためにも日本語力はあるに越したことはありません。
こども新聞を活用してメキメキ日本語能力を伸ばしていきましょう!
我が家が選んだ読売KODOMO新聞は週刊なので負担が少なく、小学校低学年にはちょうど良い分量でおすすめですよ。
